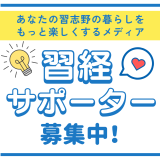習志野・子安神社で神事「おびしゃ」 弓を放ち刺さった場所で吉凶占う

子安神社(習志野市藤崎2)で2月7日、矢を射て吉凶を占う神事「おびしゃ」が行われた。
おびしゃとは、元々武士が歩いて弓を射る技法である「歩射(ぶしゃ)」が五穀豊穣を祈る儀式へと変化したもの。的を目がけて弓を放ち、刺さった場所で吉凶を占う。
以前までは習志野市内の複数の神社で「おびしゃ」が行われており、かつては藤崎の愛宕神社、大六天、屋敷の天津神社、鷺沼の根神社、八剱神社でも斎行していたが、コロナ禍を契機に規模を縮小。斎行自体を取りやめる地域も出ている。現在は子安神社のほか、実籾の大原神社で氏子や近隣の住民を中心に行っている。
市内の「おびしゃ」は農作物のシーズンに合わせて春に一斉に催しており、1月に大原神社、2月に子安神社で、それぞれ斎行。神社によって解釈や方法が若干異なり、実籾の大原神社では「鬼」と書かれた半紙に弓を射ることで、厄をはらう意味を持っている。「びしゃ」の字も地域や神社によって「奉射」「武社」「毘舎」など、さまざまな表記が存在する。
習志野市教育委員会文化財係の藤本光徳さんは、祭りについて、「昔は虫の発生や火山の噴火で飢饉(ききん)が起こってしまうほど、食料を得られるかどうかが自然に左右されており、そんな背景があって生まれた行事。現在は輸入やビニールハウス栽培などが発展したが、おびしゃ祭りの背景を知り、昔の人々の祈りや切なる思いを感じてもらえれば」と話す。
大原神社の権禰宜(ごんねぎ)、櫻井瑞恵さんは「もともと、『おびしゃ』は氏子の方々が主となって実施されてきた神事。現在は実籾、東習志野の周辺住民が当番で受け継いでいる。やめてしまうのはいつでもできるが、伝統として続けていくことが地域活性化にもなると思うので、これからも続けていければ」と話す。