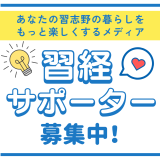八坂神社(習志野市津田沼1)で2月6日、「初午(はつうま)祭」が行われた。
初午祭は2月最初の午の日に、全国の稲荷神社で豊作や商売繁盛、開運、家内安全などを祈念して斎行される祭り。同社は以前船橋市前原に祭られていた笠間稲荷神社、京都の八坂神社の分霊を合祀(ごうし)して1924年に創建され、昨年100年を迎えた。毎年夏には夏祭りとして「八坂神社祭礼」「津田沼北口夏祭り」を催しており、市内から多くの人が集まる。
[広告]
同社の初午祭は、氏子を中心に小規模で実施。八坂神社の関係者のほか、神職は二宮神社の権禰宜(ごんねぎ)、久保田征(まさし)さんが奉仕した。
主催する津田沼一丁目町会の副会頭・髙橋勝さんは「とても寒かったので、皆さんの体調が気になったが、無事斎行できて良かった。今年は社務所の建て替えを予定しており、夏祭り後から解体するので、うまくいけば」と話す。
久保田さんは「初午祭は、創建の神主・秦一族が初午の日にお稲荷さまを祭っていたのが始まり。周辺の方々からたくさんの信仰を頂いているので、皆さまの発展、隆昌を祈念している」と話す。また、「今年の干支(えと)は60年周期のうちの乙巳(きのとみ)で、歴史の中では大化の改新が起きた年。大きな変革をもたらす年、人々の抱える病が少しずつ改善に向かう年で、財力、知力ともに向上するといわれている。皆さまにはそうした力を大いに受けてもらえれば」とも。